(写真は先日の帰り道に撮ったものです。
家からほど近いヴァポレットの桟橋サン・ザッカリアを降りたときにちょうど夕暮れ時できれいだったので撮りました)
音楽院の先生とは別の先生に師事する機会がありました。
バロック声楽科の大学院の学生とマドリガーレをデュエットすることになりまして、彼女が音楽院の外で習っている先生です。
仮にA先生と呼ぶことにします。
A先生はオルガン科のディプロマを持っていますが、過去に声楽も学んでおり、現在はフェニーチェ劇場の合唱で歌っています。
とはいえ劇場の仕事は生活のためで、彼女の情熱は古楽にあるそうです。
自宅にはチェンバロがあり、1600年代の初期バロックのマドリガーレも指導してくださいます。
というわけで習ってきたのですが、音楽院でふだん習っている先生とかなり異なる発声指導で驚きましたので、記事にしてみました。
その違いが「古楽か否か」なのかは分かりません。
ただ彼女の導きで発声すると、結構オペラティックなビブラートが意図せずかかるようになります。
テキストの発音か、声の響き&声量か
A先生、チェンバロ奏者のレッスンのような音楽的な指導、スタイルに関する指導だけをされるのかと思ったら、がっつり発声を見るタイプだったので意外でした。
「美しい声として目指すゴールは皆同じ、ただアプローチが違うだけ」――というのが理想論かと思うほど、声楽というのは先生によって発声指導法が異なるのです。
なぜこれほど異なるのかというと「良い歌唱には何が不可欠か」というアイディアが違うからかも知れません。
音楽院の古楽の先生に声楽を習ってきて、いつも言われているのは「言葉が大切」ということです。
当然発音に重きを置くし、歌い上げるよりしゃべるニュアンスを大切にすることが多い――ルネサンスものか、後期バロックのオペラアリアか、などジャンルによって異なる部分もあるのですが、程度の差こそあるもののテキストの重要性はいつも言われています。
オペラが言葉を大切にしないとは思わないのですが、劇場で歌っているA先生は、それ以上に声の響きを求めます。
響きがつくと、音量も大きくなって聞こえますので、オーケストラピットを飛び越える発声かもしれません。
A先生に言われたのは、
「オペラ歌手の発音なんて、何言ってるか分からないでしょ?」
というもの。
イタリア人の彼女が聴いても、イタリア人ソプラノ歌手の発音は不明瞭だと言います。
まあ…確かにそうですけどね。
しゃべるときのように声を前に持っていくのではなく、口の中をドーム状にして口の中や頭蓋骨で響かせる――そのとき発音が犠牲になっても美しい響きを得られるというわけ。
音楽院の古楽の先生のメソードでは、正しい形の母音を作ることが自然な美しい響きにつながるので、上記のように声をカバーする(コペルトする)テクニックは使いません。
両方の先生に習っているデュエットの相手の学生に、
「音楽院のレッスンでもA先生のテクニックで歌ってるの? B先生は何て言ってる?」
と訊いたところ、
「もっと声を前に出しなさいって毎回言われるよ」
とのことでした。
詳しくは、論文の要約と感想を書いた以下の記事で!
顔の筋肉をリラックスさせるか、頬骨を高く保つか
音楽院のレッスンでは、自然な表情が大切だと言われます。
たとえ難しいことをしていても、聴く人にはナチュラルに見えなければいけません。
目をかっぴらいたり、しかめっつらをしたり、普段の生活ではあけないような大口をあけてはいけないのです。
オペラにおいても表情筋のリラックスは、完全に無視してよいわけではないと思います。
でも頬骨をできるだけ高く保つことで、響きを明るくするテクニックを教わりました。
このテクニックを使うと、いつもの「ひたすら自然に! 顔の筋肉をリラックス!」を意識するのとは、違うポジションになります。
おそらく、口の中で響かせるだけだと音がこもってしまう危険性があるので、頬骨を高くすることで、後ろだけでなく前の響きも足しているのかなと思いました。
古楽の発声は文献にもとづいているのか?
バロック時代の声楽の教則本と言えば、ピエール・フランチェスコ・トージと、ジャンバッティスタ・マンチーニのものがあります。
(↓以下はトージの教則本)
(マンチーニの教則本は絶版になって久しいので国立国会図書館を利用しましょう→国会図書館のリンク)
どちらも日本語訳を読んでみましたが、これらの文献を読んだからと言って、バロック時代の名歌手の声がイメージできるわけでは勿論ないし、どんな発声をしていたか分かるような具体的なものではないと感じました。
当時大切にされていた美的感覚は分かるものの、いつの時代にもあてはまる「あるある」と言いたくなるような良い声の条件、良い歌手とは、良い教師とは、と言った話が書かれています。
A先生から訊かれました。
「Bはあなたにこれらの本を読めと言ったの?」
「いや、言われてないですね・・・」
「じゃあ彼女の発声テクニックの根拠は何? 昔はこういう声で歌っていたという論拠なんてどこにもないじゃない」
と早口のイタリア語で畳みかけられ、あれ?古楽の声なんてあるんだっけ? と、このときは少し混乱しましたが、あとから考えてみたら使う楽器の違いなどで自然に発声が変わるのかなと思います。
ただ、歌う時の自然な表情や、正しい母音の形については、文献でも触れられていたはずです。
ただ、ベネデット・マルチェッロの『当世流行劇場』に、
「台本作家への助言:ヴィルトゥオーゾの歌う歌詞が聞き取れなくても、発音を良くするように言ってはいけない。なぜなら歌手たちの歌唱から歌詞が聞き取れるようになったら、台本の売り上げが落ちてしまうから」という風刺があらわれるぐらいなので、当時から歌手たちの発音の悪さは一般的だったのかもしれません。
楽器と声楽の関係から
A先生の発声指導は、ある程度以上の広さのある劇場で歌ったり、モダン楽器のオーケストラと共演するときに”聞こえる”テクニックだと思います。
でも今回デュエットするマドリガーレはリュートの伴奏で歌います。
リュートは音量の小さい楽器です。
何と比べるかによりますが、普段チェンバロ伴奏に慣れていると、とても小さく感じますが、典雅でたおやかで大変美しい音色です。
リュートの先生と、リュートの学生とリハーサルをしていると、リュートの先生が一音一音の音色に大変気を配っていることがよく分かります。
美しい音色で鳴らすという非常に繊細な演奏が求められます。
そして歌っている我々は「もっと小さな声で!」と言われます。
大声を出したり、無駄にビブラートのかかった響きのある声で歌ったら、リュートの繊細な音色をかき消してしまうからです。
こうした古楽器とアンサンブルをしたり、マドリガーレなど対位法の曲を数人で響きを合わせて歌ったりするために、古楽科で習う発声は、いわゆるオペラ的な発声と異なるのかなと思いました。
と言っても――「いわゆるオペラ的な発声」の一言で言っても、モーツァルトを歌うとき、プッチーニを歌うとき、それぞれに適した発声をひとくくりにはできませんね。
おわりに
今回感じた違いが、古楽の発声 VS ロマン派の発声なのかは分かりません。
というのも、これを本当に検証しようと思うなら、古楽の先生10人とオペラ歌手10人に師事しました――みたいなプラティカルな研究が必要になるからです。
一人ずつの先生を比べたってどうしようもないとは思いつつ、「言葉なんて分からなくてよい」という発言に衝撃を受け、理想とする概念が古楽の世界とは異なるのではないかと思って、記事にしてみました。
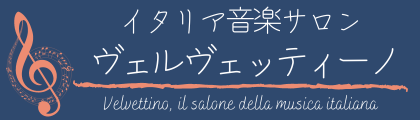



コメントを残す